『壱岐名勝図誌』【市指定文化財】〔時代:近世江戸時代末期〕
|
|
|
第35代平戸藩主〔松浦熙(まつらひろむ)(1806年〜1841年)〕の依頼を受けた壱岐の後藤正恒(ごとうまさつね)と吉野尚盛(よしのまさもり)が11年の歳月をかけて作った史料です。内容は村の広さ、産物、地名の由来、田畑の面積、家の数、人口、神社や寺などを地域別に歩く道順に沿って書いてあります。先に書かれていた『壱岐国続風土記(いきこくしょくふどき)』の書き漏れや説明不足を補ってつくられた史料です。 |
|
|
|
|
|
4165枚の銅銭が入れられた壺【市指定文化財】〔中世〜近世〕
|
|
中世の日本では、海外で鋳造されたお金が流通し、人々は手に入れたお金を貯めておくために壺などに入れて地中に埋めて保管していました。島内の郷ノ浦町平人触の畑から、お金が入れられた壺と4,165 枚の銅銭が見つかりました。銅銭は中国のお金が主流ですが、中には朝鮮半島やベトナム地域、琉球のお金なども含まれています。琉球の2枚の通貨は、15世紀に琉球王朝が発行した貨幣で、一般に流通したものではなく、記念銭として用いられた「幻の通貨」と云われるものです。 |
|
|
|
|
|
高麗版大般若経〔初彫本〕【国指定重要文化財】〔中世〕
|
|
大般若経600巻は、大蔵経(だいぞうきょう)の一部で、唐(とう)〔中国〕の時代に三蔵法師(さんぞうほうし)が漢字に訳したものです。1011(顕宗2)年頃に、高麗国で大般若経の版木を製作します。この版木を使って刷られたものを「高麗版大般若経」と呼び、1232年に起きた蒙古軍との争いで大般若経の版木が焼失するまでにつくられたものを「初彫本(しょちょうぼん)」といいます。安国寺に伝わる高麗版大般若経の最後に「重熙(じゅうき)15年〔=1046年〕」と書いてあることから、この年に作られたことがわかり、版木が製作されて約30年後につくられた初彫本としても貴重な資料です。 |
|
|
|
|
|
石造弥勒如来坐像〔複製〕【実物は国指定重要文化財】〔古代平安時代末期〕
|
|
この石仏は、弥勒如来(みろくにょらい)という仏さまです。1071〔延久3〕年につくられたもので、当時、壱岐を治めていた佐伯良孝(さえきよしたか)が、肥後国〔現在の熊本県〕の慶因(けいいん)という仏師に作らせたものです。石仏の体内は空洞にして「法華経」の経典を納め、56億7千万年後に現れると信じられていた弥勒如来という仏さまに救ってもらうために土の中に埋めたものです。現存する日本最古の「作った人の名が刻まれた石仏」としても有名です。 |
|
|
|
|
|
壱岐国分寺出土軒丸瓦〔古代〕
|
|
壱岐国分寺跡からは12,000 点以上の瓦が出土しています。この軒丸瓦は国分寺の瓦の先端に取り付けられた文様が入れられた瓦です。壱岐嶋分寺の軒丸瓦は、大宰府と同じ瓦ではなく日本の政治の中心だった奈良の平城京(へいじょうきょう)と同じ版木で作っているのが特徴です。 |
|
|
|
|
金銅製亀形飾金具(かめがたかざりかなぐ)【国指定重要文化財】〔古墳時代〕
|
|
扁平な亀形の装飾品で、頭や甲羅の形からスッポンを模したものと思われます。「鶴は千年、亀は万年」と言われる様に昔から長寿の象徴とされ、神仙世界と現世とを結びつける動物と考えられてきた「亀」をモチーフとした世界で1つの飾り金具です。 |
|
|
|
|
金銅製轡(くつわ)【国指定重要文化財】〔古墳時代〕
|
|
轡は大きく分けて、馬の口に噛ませる銜(はみ)、銜が左右にずれない様にする鏡板(かがみいた)、手綱を結びつける引手金具(ひきてかなぐ)の3つの部品で構成されています。
鏡板にはハート形の中に唐草文の模様を施しているのが特徴です。 |
|
|
|
|
金銅製辻金具(つじかなぐ)と雲珠(うず)【国指定重要文化財】〔古墳時代〕
|
|
辻金具と雲珠は、いずれも馬具をつなぎ留める皮ひもを交差させた部分を固定する役割を果たすものですが、脚が四方向以下のものを辻金具、それ以上のものを雲珠と呼んでいます。辻金具の中央にイモガイの螺頭〔らとう〕部分を輪切りにして宝珠〔ほうじゅ〕形の装飾を取り付けた飾りをはめ込んでいるのが特徴です。 |
|
|
|
|
金銅製杏葉〔ぎょうよう〕【国指定重要文化財】〔古墳時代〕
|
|
杏葉は皮ひもの先に取り付けて馬の腰や胸の前の部分にぶら下げる装飾品です。ハート形の中に唐草文の模様を施しています。 |
|
|
|
|
金銅製単鳳環頭大刀柄頭〔たんほうかんとうたちつかがしら〕【国指定重要文化財】〔古墳時代〕
|
|
大刀(たち)の柄の先端部に取り付けられた飾りで、2匹の龍が交差する装飾が施された環状部分の内部に珠〔たま〕を咥〔くわ〕えて横を向いた形の鳳凰が入っています。日本だけでなく韓国の古墳からも同形の柄頭が出土しています。 |
|
|
|
|
朝鮮系無文土器(ちょうせんけいむもんどき)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
朝鮮半島で製作されていた土器です。弥生土器と同じ野焼きの製法で製作されています。
作り方は同じですが、高度な技術でつくられているため、弥生土器より硬質に仕上がっています。これらの土器は、交易品を入れる容器として一支国に運ばれてきましたが、その役割を終えると、日常生活の中で煮炊き用の容器や器(うつわ)として再利用されていました。 |
|
|
|
|
瓦質土器(がしつどき)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
朝鮮半島の国で製作されていた土器です。あな窯を使ってつくっているため、土器は硬質(こうしつ)で、灰色に近い色に仕上がっています。また、口の部分が小さくつくられているため、液体など溢(こぼれ)やすいものを入れる容器として適していました。 |
|
|
|
|
権(けん)【日本最古】〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
権はさおばかりの錘(おもり)として用いられました。さおばかりは交易を効率よく行うために用いられました。権の重さと皿にのせたモノの重さが同じになったところでモノとモノの交換が行われていました。 |
|
|
|
|
貨泉(かせん)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
当時の一支国では、モノとモノを交換する社会だったため、通貨による交換の概念が存在しなかったことから、通貨も交易品の一つとして一支国に持ち込まれていました。交換されたお金は、通貨としてではなく、祭祀(まつり)などで使われていました。約2000年前に中国で使われていた通貨で、紀元後14年にはじめて造られたお金です。 |
|
|
|
|
車馬具(しゃばぐ) 【日本最古】〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
車馬具は、馬車の車輪(しゃりん)を留めるための部品です。当時の中国ではすでに馬車が道路を走っていましたが、倭国にはまだ馬車が伝わっていませんでした。車馬具は青銅でつくられていたため、珍しい交易品として一支国に運ばれてきたのではないかと考えられています。 |
|
|
|
|
三翼鏃(さんよくぞく) 【日本最古】〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
三翼鏃は、機械仕掛けの弓〔弩(ど)〕に用いる矢の先端に取り付けられた鏃(やじり)です。当時の中国では、戦いなどで弩は武器として使われていましたが、倭国にはまだ伝わっていませんでした。三翼鏃が青銅でつくられていたため、珍しい交易品として一支国に運ばれてきたのではないかと考えられています。 |
|
|
|
|
とんぼ玉【日本最古】〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
とんぼ玉は青色の本体に、白色の文様をつけています。側面に、丸もしくは二重丸の文様が3つ施(ほどこ)され、丸の中心には、薄い青色のガラスが装飾されています。丸と丸の間には、2つの点が施され1つのとんぼ玉として完成しています。 |
|
|
|
|
鉄鎚(かなづち)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
鉄製のかなづちです。熱く熱した鉄を叩いて加工するときに用いられました。中央には持ち手の棒をつけるための穴が開けられています。 |
|
|
|
|
銅鏃(どうぞく) 【日本最多】〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
銅鏃は、石や骨でつくられた鏃(やじり)と比べ、倍以上の威力がある特別な鏃です。現段階で、一支国内から約160本の銅鏃が見つかっており、日本最多の出土量として注目されています。 |
|
|
|
|
ト骨(ぼっこつ)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
ト骨占いはシカやイノシシの骨に焼いた木の棒を押しつけて、骨に入るヒビの入り方をみて吉凶を判断しました。このト骨には焼いた木の棒を押し当てた時に付いた黒斑(こくはん)が残っています。 |
|
|
|
|
人面石(じんめんせき) 【日本唯一】〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
人面石は、人の顔を模してつくられおり、ノルウェーの画家ムンクが描いた「叫び」に似ています。2つの目は石の半分まで彫り込まれ、口は裏まで貫通しています。目の上には眉が、目と口の間には鼻が彫られています。 |
|
|
|
|
捕鯨線刻土器〔壺〕(ほげいせんこくどき〔つぼ〕)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
甕棺に転用(てんよう)された壺には舟の画とクジラの画が描かれています。土器の外面にはクジラに銛(もり)が3本刺さっている様子が描かれています。土器の内面にもクジラの画が描かれており、捕鯨を行っている様子を描いた線刻土器と考えられています。 |
|
|
|
|
竜線刻土器〔壺〕(りゅうせんこくどき〔つぼ〕)〔弥生時代〕 【国指定重要文化財】
|
|
この壺には2匹の竜と雷(かみなり)の稲光(いなびかり)の様子が描かれています。1匹の竜は、反り返るように宙(そら)を自由に動きまわっている様子が、もう1匹の竜は体を巻いて丸くなった様子が描かれています。 |
|
|
|
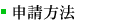 |
|
| 1. |
用紙サイズはあらかじめ設定していますが、ご利用のパソコンの設定によって、設定と異なる用紙サイズで印刷されることがあります。必ず指定の用紙サイズで印刷したものをご利用ください。市が設定したサイズと異なって印刷されている場合は、改めて窓口で書類に再記入・押印していただく場合があります。 |
| 2. |
ホームページ上で申請を受けつけるものではありません。申請の際は、作成した申請書等を各窓口までお持ちいただくかもしくは郵送にて提出してください。 |
| 3. |
「申請書提供サービス」は、すべての申請書を提供するものではありません。インターネットで提供が可能な申請書を提供しています。 |
| 4. |
申請書の様式は変更することがあります。ご利用の際は、最新の様式をダウンロードしてください。 |
| 5. |
用紙は普通紙をご利用ください。感熱紙での受付はできません。 |
|
 |
各申請書ファイルを参照するには、Adobe Readerが必要です。左のリンクからビューワーソフトを入手できます。 |
|
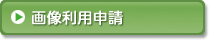 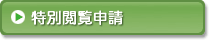 |
|

